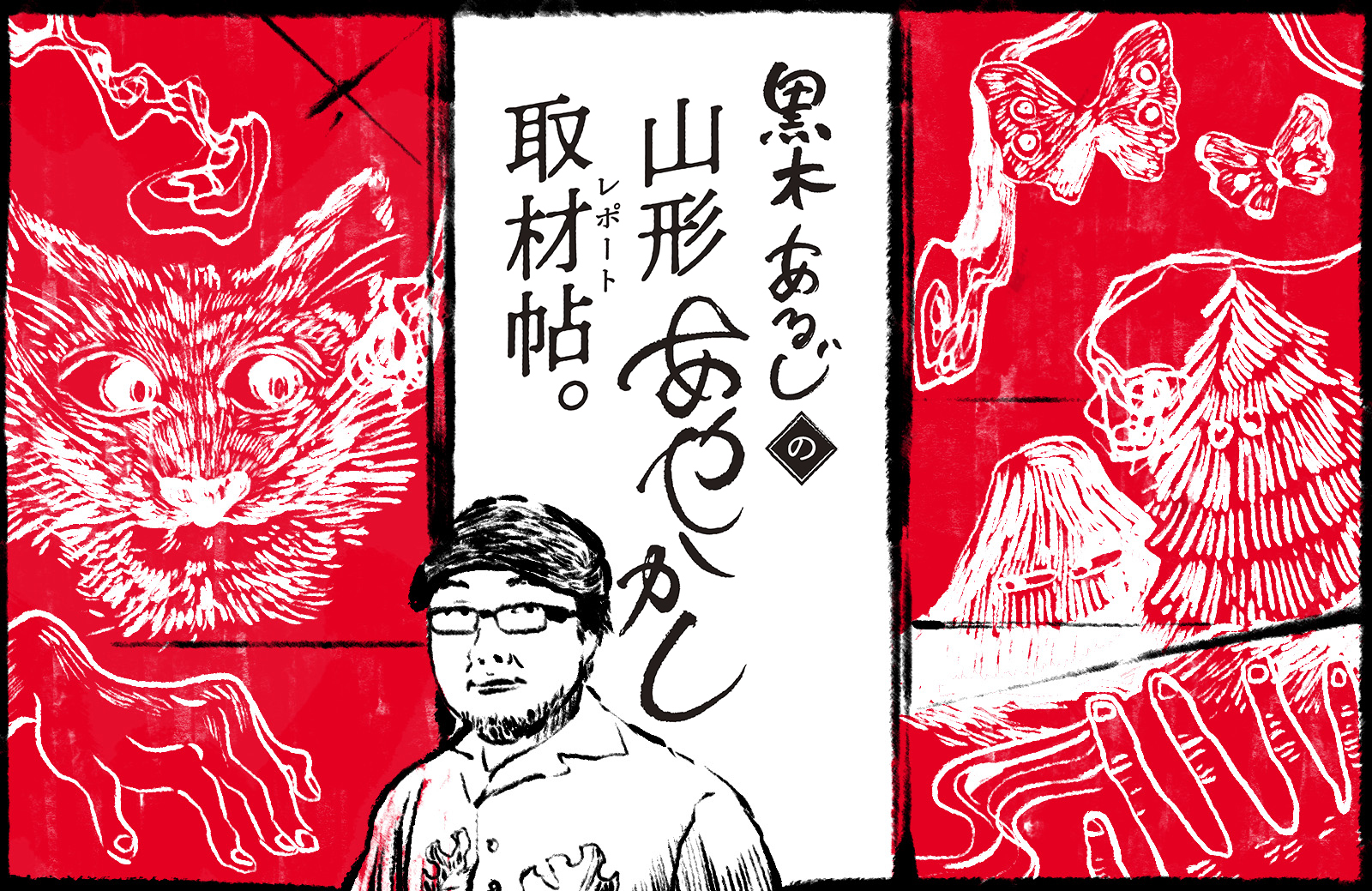だれかの散文|黒木あるじの山形あやかし取材帖
新しい年には縁起物が欠かせない。その筆頭といえば鶴と亀になるだろうか。鶴は古代中国で仙界に棲む鳥とされ、神仙の話を集めた『淮南子』の説林訓にも「鶴の寿は千歳」とある。また、8世紀に皇族が住んでいた邸宅跡地から鶴の描かれた土器が出土している。はるか古より、日本ならびに中国では鶴は瑞鳥であったようだ。亀もまた不老と長寿の象徴として崇められている。天の一端を司る霊獣・玄武は蛇が巻きついた亀の姿で描かれる場合が多い。奈良県明日香村にあるキトラ古墳の壁にも玄武が確認されている。亀もまた鶴とおなじく、古くより寿のシンボルだったのである。
山形にも鶴亀の伝承は数多く残っている。とりわけ有名なのは南陽市の「鶴の織機」だろうか。同市にある鶴布山珍蔵寺は、鶴の化身である女房が織った毛織物がいまも寺宝となっている。民話「鶴の恩返し」のルーツを標榜する場所は全国にあるものの、物証が現在も残っているというケースは珍しい。
だが、冷静に考えれば「千年生きる鶴、万年生きる亀」とは、なかなかどうして怪しい存在ではないだろうか。異様な長命をほこる2種の生物──その周辺に不気味な話があったとしても、なんら不思議はないのだ。
今回は、そんなめでたくも怪しい話をふたつお届けしよう。
第壱話
まずは、千年生きる鶴の話から始めよう。「いくらなんでも、そんなに長生きする鳥などいるものか」と笑う向きもあるはずだ。さよう、鶴の平均寿命はおよそ80年とされている。しかし、それが由緒正しき鶴であったとなれば、話は違ってくる。
《江戸の頃の話である。川北(現在の酒田市から遊佐町周辺)に住む久右ェ門という鳥撃ちが、あるとき一羽の鶴を撃ち殺してしまった。その鶴はひどく老いており、身体は骨のようであったという。どれほど長生きの鶴なのかと驚いていた久右ェ門は、鶴の一部が金色に光っていることに気づいた。よく見れば光る箇所には〈頼朝飼鶴五十ノ内〉の文字が書かれている。不思議に思い御家の土田市右ェ門に献上したところ、なにかを察した市右ェ門はその鶴を土塁に埋めてしまったそうである。(『大泉百談』杉山宜袁著・大泉散士訳)》
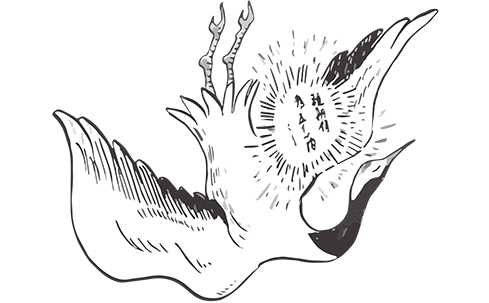
源頼朝が自分の名を記した鶴が江戸時代の山形で発見される──にわかには信じ難い話だが、この物語はいくつかの背景を知った上で読むと非常に興味深い。
まず、くだんの逸話は「放生会」にちなんでいるとおぼしい。放生会とは殺生を戒める仏教の教え「殺生戒(せっしょうかい)」にもとづき、捕獲した鳥獣や魚を解放する儀式である。その起源は中国の天台宗開祖とされており、『日本書紀』にも天武天皇の記録として「諸国に詔(みことのり)して放生せしむ」と記されている(実際におこなわれたのは720年、宇佐八幡宮だとする説もある)。現代でいう動物愛護と共通した考えは古くから存在したのである。
では、なぜ頼朝の名前があるのか。実は源頼朝は1187年に上洛する際、鶴千羽の足に金の短冊をつけて空へ放ったと記録されているのだ(このときの放生会が現在の鶴岡八幡宮例大祭になったとの説もある)。つまり上記の物語は、史実を下敷きに「鶴の長命」を証明するという、なかなか凝った造りになっているのである。
いっぽう、この話にはどこか不穏さも漂っている。それほど目出度い鶴を見つけたというのに、なぜ土田市右ェ門なる男はその遺骸を埋めてしまったのだろう。瑞鳥を殺してしまった事実を隠蔽しようとしたのか、それとも鳥の容姿にただならぬものを感じての措置なのか。答えは分からぬままだが、庄内のどこかに数百年を生き延びた鶴の亡骸が埋葬されているかもしれない──とは、なかなかどうして不気味なロマンに満ちている。
底本としたのは、本稿ではおなじみの『大泉百談』。荘内藩の奉行所に勤めていた杉山宜袁(よしなが)がまとめた庄内の記録を、昭和になって大泉散士という書店主が訳したものだ。藩の性格なのか、庄内藩はありとあらゆる事柄を記録するふしがあり、今回の話以外にもあまたの奇談が残っている。令和に生きるお化け屋としては、なんともありがたいばかりである。
第弐話
続いては、万年の命を持つ亀の話を。こちらは永禄年間に開山した新庄市の古刹、長泉寺の縁起とされる伝説で、「新庄祭り」の山車の題材としてもたびたび扱われている。とはいえ登場する亀はなかなかどうして禍々しい。なんとこの亀、人間を喰うのである。

《新庄城が築造される以前、沼田城(現在の最上公園周辺)にはその名のとおり巨大な沼が広がっており、そこには恐ろしい大きな亀が生息していた。この大亀、ときおり陸上へ這いあがってきては道行く人を捕らえ、食べていたのだという。そのため沼の近くを通る者は絶え、一体はなおのこと寂しい空気に包まれてしまった。
あるときのこと、ひとりの高僧が人食い亀の話を聞きつけ「仏の功徳でなんとかしましょう」と沼のそばに庵を建て、昼となく夜となく一心に読経を続けた。しばらく経ったある日、白衣をまとった幼な子が高僧の前に姿を見せ、読経を聞き終えるや沼に身を投げてしまった。するとそれ以降、人食い亀は姿を見せなくなったのである。以来、高僧を慕って帰依する者が増え、庵はやがて寺へと改修、現在の「亀棲山長泉寺」になったということである。(『最上地方伝説集』大友儀助編)
長泉寺は、亀綾織の三十三観音掛仏や文殊菩薩像など市指定の文化財も残る名刹。その由来が〈人喰らう亀〉というのは、なんとも面白い。日本には年経た器物が化ける「付喪神」信仰があった。万年を生きる亀なら人を食うほどの怪物に変化しても不思議はないと思われていたのだろうか。
恐るべきことに、人食い亀の話は全国各地に伝わっている。たとえば島根県松江市にある月照寺には、池に住んでいた亀が夜な夜な城下の子供を食い続け、寺の住職が大亀の石像を藩主の墓所に安置したところ人食いを止めたとの話が残っている。また、広島県尾道市の生口島に棲む亀の総大将「亀主」は、船を襲い人を食べていたが、寺の小僧がその首を切り落としたとの伝承がある。亀主の首は海へ飛び去って巨岩となり、その付近では海難事故が多発したため、亀主の霊を供養する地蔵が建てられたという。いずれも仏教と深いつながりを持っているあたりが興味深くもある。
興味深いといえば、不老の象徴たる大亀が童子の姿で出現した点も気になってしまう。岩手県二戸市には、足利尊氏から逃れてきた万里小路藤房の子・亀麿が夭逝したとの言い伝えがある。亀麿は死の間際「末代まで家を守る」と言い遺し、のちに座敷わらしになったともいわれている(座敷わらしで有名な金田一温泉には亀麿神社が祀られている)。さすがに沼田城の大亀とゆかりはないだろうが、「亀=童子」のヒントがなにかしら隠されているようにも思えてしまう。
『最上地方伝説集』は、雪の里情報館の館長も勤められた大友儀助氏が昭和44年に刊行した伝説集である。大友氏は県文化財保護審議会委員、県総合政策審議会委員なども務めた、最上地方の文化(とりわけ雪にまつわる風土)研究の第一人者だが、民話や伝説の収集にも熱心であった。この時期に彼が集めた伝説・伝承の多くは、いまや語り手を喪い二度と聞くことができない。かつて雪の里で語り継がれてきた物語を知ることのできる、きわめて貴重な一冊といえるだろう。

黒木あるじ
怪談作家。1976年青森県弘前市生まれ。東北芸術工科大学卒。池上冬樹世話役の「小説家(ライター)になろう」講座出身。2009年、『おまもり』で第7回ビーケーワン怪談大賞・佳作を受賞。同年『ささやき』で第1回『幽』怪談実話コンテストブンまわし賞を受賞し、2010年に『震(ふるえ)』でデビュー。